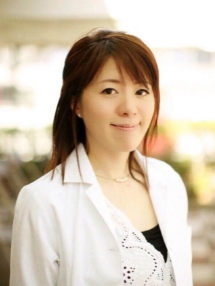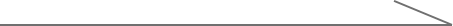妊娠糖尿病にひっかからないために気を付けるべき生活習慣
祝日診療。自由が丘・奥沢の内科・糖尿病内科・訪問診療・各種健診なら当クリニックへ。
祝日
診療
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ★ | ー | ● |
| 14:30-18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ● |
※受付は15分前終了 ★9:30~13:30(13:15最終受付)
祝日
診療
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ★ | ー | ● |
| 14:30-18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ● |
※受付は15分前終了 ★9:30~13:30(13:15最終受付)
妊娠糖尿病にひっかからないために気を付けるべき生活習慣
2025/04/18

妊娠糖尿病とは、妊娠中に初めて発見される糖代謝異常のことを指します。
これは、妊娠によるホルモンの変化が原因で、インスリンの働きが弱まり、血糖値が上昇しやすくなる状態です。妊娠中は胎盤から分泌されるホルモンが増加し、インスリンの効果を抑制するため、血糖値のコントロールが難しくなります。
妊娠糖尿病は、母体や胎児にさまざまな影響を及ぼす可能性があるため、早期の発見が重要です。
糖負荷試験でひっかからないために知るべきこと

妊娠糖尿病の診断には、糖負荷試験(OGTT)が用いられます。
この検査では、一定量のブドウ糖を摂取し、その後の血糖値の変化を測定します。検査前の食事や睡眠、ストレスなどが結果に影響を与えることがあるため、検査前日は規則正しい生活を心がけることが大切です。
また、検査当日は空腹で受ける必要があるため、朝食を抜いて受診するようにしましょう。糖負荷試験でひっかからないためには、日頃からの生活習慣の見直しが重要です。
妊娠糖尿病の原因とリスク
妊娠糖尿病の原因は、妊娠によるホルモンの変化や、インスリンの働きが弱まることなどが挙げられます。また、以下のようなリスク要因があると、妊娠糖尿病の発症リスクが高まります。
- 肥満や過体重
- 家族に糖尿病の人がいる
- 高齢出産(35歳以上)
- 過去に妊娠糖尿病を経験したことがある
- 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の診断を受けている
これらのリスク要因がある場合は、妊娠前からの生活習慣の見直しや、医師との相談が重要です。
妊娠糖尿病にひっかからないための食生活

妊娠糖尿病の予防には、まず1日3回の食事を欠かさず摂ることが大前提です。
食事を抜くと、次の食事で急に血糖値が上がりやすくなり、身体への負担が大きくなります。特に朝食を抜くと、昼食時の血糖値が急上昇しやすく、妊娠糖尿病のリスクが高まる要因となります。毎日決まった時間に食事をとることで、体内の代謝リズムが安定し、インスリンの働きもスムーズになります。お腹の赤ちゃんに必要な栄養を効率よく届けるためにも、食事のタイミングを一定に保つことが重要です。
血糖値の上昇を防ぐ食べ方の工夫
血糖値を上げにくくするための「食べ方」も大切なポイントです。
たとえば、野菜や汁物を先に食べる「ベジファースト」を実践することで、糖の吸収がゆるやかになり、食後の血糖値上昇を抑える効果があります。野菜に含まれる食物繊維は、糖質の吸収を緩やかにする働きがあります。サラダや煮物、具だくさんの味噌汁などから食事を始めることで、インスリンの負担を減らすことができます。
また、よく噛んでゆっくり食べることも重要です。早食いをすると、満腹感を感じる前に食べ過ぎてしまい、血糖値が急激に上がる原因になります。一口ごとに30回程度噛むことを意識すると、自然と食べるスピードが落ちて血糖値の安定にもつながります。
炭水化物と甘い物の付き合い方
妊娠中はエネルギーが必要な時期ですが、炭水化物を摂りすぎると血糖値が乱れやすくなります。特に白米や白パンなどの精製された糖質は、GI値が高く血糖値を上げやすいため注意が必要です。主食は、玄米や雑穀米、全粒粉パンなどに置き換えると、血糖の上がり方がゆるやかになります。
また、甘いお菓子やジュース、菓子パンなどは血糖値を急激に上げるうえ、栄養価が偏りがちです。どうしても甘いものが食べたくなった時は、果物やナッツ、無糖ヨーグルトなどを選ぶようにしましょう。これらの食品は血糖値への影響が比較的穏やかで、栄養補給にも役立ちます。
妊娠糖尿病を防ぐ食品の選び方

妊娠糖尿病の予防には、食べ方だけでなく、日々の食材選びがとても大切です。どんな食品を選ぶかによって、食後の血糖値の上がり方やインスリンの働き方が大きく変わってきます。
特に妊娠中は、血糖値が上がりやすい状態にあるため、血糖の上昇を穏やかにする食品や、腸内環境を整える栄養素を意識的に取り入れることがポイントになります。ここでは、妊娠糖尿病のリスクを下げるために、日常の食事で選びたい食品の特徴や選び方について、詳しくご紹介します。
食物繊維を豊富に含む食材を意識する
食物繊維は、血糖値の急上昇を防ぐうえで非常に効果的です。
水溶性と不溶性の2種類があり、どちらもバランス良く摂取することが望ましいとされています。水溶性食物繊維は、海藻類や大麦、こんにゃくなどに多く含まれ、糖の吸収をゆっくりにしてくれる働きがあります。不溶性食物繊維は、野菜や豆類、きのこに多く含まれ、腸内環境の改善や便通の促進に役立ちます。
たとえば、夕食の一品としてひじきの煮物や、朝食に納豆と味噌汁を取り入れるだけでも、食物繊維の摂取量をぐっと増やすことができます。
毎食ごとに「野菜を一皿以上」加えることを意識してみましょう。
GI値の低い食品を選ぶ
GI値(グリセミック・インデックス)が低い食品は、血糖値の変化が緩やかでインスリンの分泌にも優しい食品です。
たとえば、主食に使われる米なら白米よりも玄米や押し麦入りの雑穀米が、パンであれば全粒粉のものが推奨されます。麺類を選ぶ際には、うどんよりもそばの方がGI値が低い傾向にあります。
また、芋類や果物も選び方が重要です。じゃがいもやバナナはGI値が高めなので、さつまいもやりんごなどの方が血糖値に与える影響が緩やかです。GI値を意識した食品選びは、無理のない血糖管理につながります。
発酵食品で腸内環境を整える
妊娠糖尿病の予防には、腸内環境を整えることも効果があるとされています。
発酵食品に含まれる乳酸菌や納豆菌などの善玉菌は、腸内のバランスを整えるだけでなく、インスリンの感受性を改善する働きもあります。毎日の食事に味噌汁や納豆、ヨーグルトなどを加えるだけでも、大きな効果が期待できます。
腸内環境が整うと、血糖の変動が穏やかになるだけでなく、便秘の予防や免疫力の向上にもつながります。体調を安定させるためにも、積極的に取り入れていきたい食品群です。
➤ 世田谷内科・糖尿病総合クリニックの栄養指導とは?(院内キッチンあり)
尿糖が出たときの対処と予防
妊婦健診で「尿糖が出ています」と言われると、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。とくに初めての妊娠では、「妊娠糖尿病なのでは?」と心配になることもあるかもしれません。
しかし、尿糖の検出は必ずしも異常というわけではなく、妊娠中の身体の変化によって一時的に出ることもあります。大切なのは、その原因を冷静に理解し、必要な対処を取ることです。
尿糖が出たときに考えられる理由と、その改善・予防のためにできる食事や生活習慣の見直しポイントを、やさしくわかりやすく解説します。
妊娠中に尿糖が出る原因とは
妊娠中に尿糖が出たと言われた場合、それだけで妊娠糖尿病と診断されるわけではありません。妊娠に伴い腎臓の働きが変化するため、通常よりも血中の糖分が尿に漏れやすくなることがあります。これは「妊娠性尿糖」と呼ばれ、血糖値が正常範囲内でも尿糖が検出されるケースです。
しかし、繰り返し高い尿糖が続く場合や、他の症状と併発している場合には、血糖値の異常が隠れている可能性もあります。そのため、尿糖の結果だけで安心せず、必要に応じて追加の血液検査や糖負荷試験を受けることが勧められます。
尿糖が出たときの食生活の見直し
尿糖が検出されたら、まずは日常の食生活を振り返ってみましょう。
甘いお菓子や砂糖の多い清涼飲料水、菓子パンなどを頻繁に摂っていないか、間食の回数が多くなっていないかを確認します。また、1回あたりの食事量が多すぎていないか、血糖値を急上昇させる食べ方になっていないかも重要なポイントです。
夜遅くの食事や、空腹状態で一気に食べるような習慣も、尿糖が出る一因となります。3食をきちんと決まった時間に摂ることで、血糖の変動を穏やかに保つことができ、尿糖の改善にもつながります。
軽い運動と水分補給を心がける
食事の見直しに加えて、日常的に軽い運動を取り入れることも効果的です。
運動によって筋肉がブドウ糖を消費するため、血糖値が下がりやすくなります。無理のない範囲でのウォーキングやストレッチは、尿糖を改善するだけでなく、妊娠中の気分転換や体力維持にもつながります。
また、水分をこまめに補給することで、体内の老廃物が排出されやすくなります。脱水が進むと血糖が濃縮されやすくなるため、尿糖が出やすくなります。1日を通して定期的に水や麦茶を摂ることを意識しましょう。カロリーゼロの飲み物を選ぶことで、糖質の摂りすぎを防ぐことができます。
妊娠中におすすめの運動療法

妊娠中は安静に過ごすことが大切と思われがちですが、実は適度な運動は妊婦さんの体にとって多くのメリットがあります。
特に妊娠糖尿病の予防や血糖コントロールにおいて、無理のない範囲で体を動かすことはとても有効です。とはいえ、妊娠中は体調が変化しやすく、何をどの程度まで行ってよいのか不安に思う方も多いのではないでしょうか。ここでは、妊娠中でも安心して取り組める運動の種類や時間、注意点などをわかりやすくご紹介します。
安全に配慮しながら、体と心の健康を保つために、妊婦さんにとっての“ちょうどよい運動”を見つけていきましょう。
妊娠中の運動が血糖コントロールに役立つ理由
妊娠中の身体は、ホルモンの影響によってインスリンの働きが弱まり、血糖値が上がりやすくなる傾向にあります。
これが妊娠糖尿病の大きな要因のひとつです。そのため、インスリンの働きを助け、血糖値を安定させる方法として「適度な運動」が非常に有効とされています。運動をすることで筋肉がブドウ糖をエネルギーとして使うため、インスリンの分泌量に頼らずに血糖値を下げることができるのです。
これは妊娠糖尿病の予防だけでなく、すでに診断を受けている方の血糖コントロールにも重要な対策となります。
妊婦さんでも安心してできる運動とは
妊娠中におすすめされる運動は、あくまで「軽度から中等度」の強度で、身体に無理のない範囲のものに限られます。代表的なものとしては、ウォーキング、ストレッチ、マタニティヨガ、スロースクワットなどが挙げられます。
中でもウォーキングは、外に出て気分転換にもなり、全身の血行促進にもつながるため、多くの妊婦さんに取り入れられています。1日15分から30分程度の軽い散歩でも、継続することで血糖値の安定や体重管理に良い影響を与えることが期待できます。
また、室内でできるマタニティヨガやストレッチも人気です。呼吸を整えながら身体をほぐすことで、自律神経のバランスが整い、ストレス軽減にもつながります。妊娠中は体調や日によって動きやすさが異なるため、自分のコンディションに合わせて無理のない範囲で取り組むことが大切です。
運動の頻度とタイミングの目安
妊娠中の運動は、週に3〜5回程度、1回あたり15〜30分を目安にするとよいとされています。ただし、継続が何より大切なので、1日5〜10分でも構いません。
とくに食後1時間ほどのタイミングで身体を動かすと、食後血糖の上昇を抑える効果が高まりやすいといわれています。
ただし、空腹時の運動は血糖値が下がりすぎるリスクもあるため避けましょう。室内で行う運動も含め、気温や湿度の高い日は熱中症のリスクもあるため、しっかりと水分を補給しながら安全に取り組むことが重要です。
医師の許可を得て安全に行うことが大前提
妊娠中の運動は、すべての妊婦さんに適しているわけではありません。
切迫早産や前置胎盤、妊娠高血圧症候群などの診断を受けている場合や、強い貧血や体調不良がある場合は、運動を控えるべきケースもあります。そのため、運動を始める前には必ず主治医に相談し、自分の身体の状態で何が可能か、どの程度までなら安全かを確認するようにしましょう。
また、妊娠週数が進むにつれてお腹が大きくなり、バランスを崩しやすくなります。転倒などのリスクを避けるためにも、急な動作や複雑なポーズは避け、安定した動作を選ぶように意識しましょう。滑りにくい床や、転倒時に危険の少ない柔らかいマットの上で運動することも安全面で重要です。
妊娠中の運動は心と体の健康に役立つ
妊娠糖尿病の予防という側面だけでなく、妊娠中の適度な運動は、メンタル面にも良い影響を与えます。
妊娠中はホルモンバランスの変化や生活リズムの変化により、気分が不安定になったり、ストレスを感じやすくなったりする時期です。運動によって血流が良くなり、セロトニンなどの“幸福ホルモン”が分泌されることで、リラックス効果が得られやすくなります。
また、妊娠中に適度な運動習慣があると、産後の体力回復がスムーズになりやすいとも言われています。育児が始まると体力が必要になるため、妊娠中から無理のない範囲で体を整えておくことが、産後の生活を楽にする助けにもなります。
運動は無理してやるものではなく、自分のペースで心地よく続けられることが何より大切です。
妊娠前の運動習慣がある人はどうか?
たとえば、妊娠前にスポーツやダンス、ジムでの筋トレなどを定期的にしていた方は、妊娠中もある程度の身体活動に体が慣れているため、軽度〜中等度の運動を継続して行いやすい傾向があります。こうした方は妊娠中でも主治医と相談のうえで、安全な範囲で以前より軽めの運動を続けることができます。
たとえば、20代でジムに通っていた妊婦さんであれば、妊娠初期~中期まではウォーキングや妊婦向けの軽い筋トレ、マタニティスイミングなども検討可能です。ただし、妊娠の経過が順調であることが前提になります。
妊娠前にあまり運動していなかった人は?
一方で、妊娠前にほとんど運動をしていなかった方がいきなり運動を始める場合は、必ず医師に確認した上で、非常に軽い運動から始めることが勧められます。急に運動を始めると体に負担がかかりすぎたり、バランスを崩しやすくなったりするためです。
たとえば、日常的な家事の中で少し多めに歩いたり、1日10分のストレッチから始めたりと、「身体を慣らす」ような意識が必要です。特に10代や20代など若年妊婦の場合は体力がある反面、つい無理をしすぎる傾向があるため、「無理をしない」「疲れたらやめる」ことを意識して取り組むようにしましょう。
妊娠糖尿病にならないために食事・運動以外で気を付けるべき生活習慣
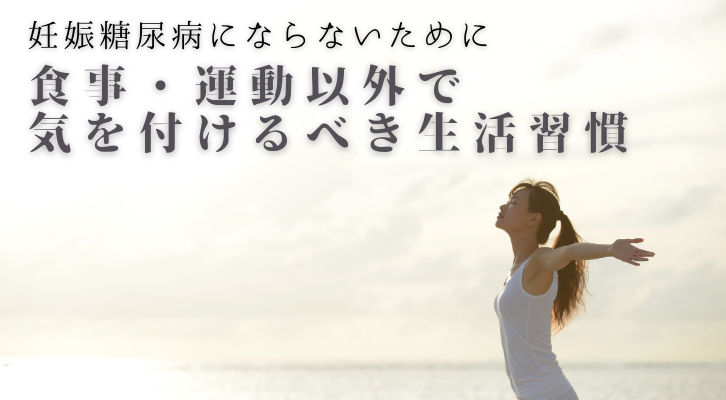
妊娠糖尿病の予防や血糖値の安定には、食事と運動の工夫が基本とされていますが、それだけでは十分とは言えません。
実は、日常生活の中にある何気ない習慣や環境の整え方が、体の代謝やホルモンバランスに影響し、血糖値の上下にも大きく関わってきます。特に妊娠中は、体も心も大きく変化する時期ですから、食べ物や運動だけでなく、生活全体の質を高めることが、妊娠糖尿病のリスクを抑えるうえで重要になってきます。
睡眠不足が血糖値に与える影響を軽視しない
妊娠中はホルモンバランスの変化により、眠りが浅くなったり夜中に目が覚めやすくなったりすることがありますが、慢性的な睡眠不足は血糖コントロールに悪影響を及ぼすことが明らかになっています。実際に、アメリカの研究では、睡眠時間の短縮がインスリン感受性の低下と関連することが示されており、妊娠中も同様の傾向が見られると考えられています。
特に夜更かしや不規則な生活は、交感神経が優位になり、コルチゾール(ストレスホルモン)の分泌が増えることで血糖値が上がりやすくなります。睡眠時間は1日7〜8時間を目安にし、夜はテレビやスマートフォンの光を控えめにし、ゆったりとした気持ちで床につくことを意識しましょう。質のよい睡眠をとることが、ホルモンバランスの安定とインスリン抵抗性の緩和につながります。
ストレスの蓄積も血糖値を乱す要因になる
妊娠中は身体の変化だけでなく、出産や育児への不安、仕事や家庭のプレッシャーなど、さまざまなストレスが重なりやすい時期です。このストレスが長く続くと、「コルチゾール」や「アドレナリン」といったストレスホルモンが多く分泌され、肝臓がブドウ糖を放出する働きが強くなって血糖値が上がりやすくなります。
この仕組みは、妊娠糖尿病の発症リスクにもつながるため、ストレスマネジメントも立派な予防策のひとつです。厚生労働省の「こころの耳」でも、妊娠中や産後のストレス対処法として、軽い運動や深呼吸、家族との会話、短時間のひとり時間の確保が勧められています。とくに日常の中でほっとできる時間を意識的に作ることが、心身の安定を保つ鍵になります。
水分をしっかり摂ることで代謝を促進する
意外と見落とされがちなのが「水分補給」の重要性です。
妊娠中は体内の血液量が増えるため、水分の必要量も自然と多くなります。脱水状態になると血液中の糖濃度が上がりやすくなり、血糖値が一時的に高くなる可能性があるのです。さらに、水分が不足すると腎機能や腸の働きが低下し、代謝全体にも影響します。
1日1.5〜2リットルを目安に、のどが渇く前にこまめに水や麦茶を飲むようにしましょう。糖質を含む清涼飲料水やスポーツドリンクは血糖値に大きく影響するため避けるのが理想です。妊婦さんの水分補給については、母子保健指導マニュアルでも「無理のない範囲で十分な水分摂取を心がけるように」と推奨されています。
サプリメントや薬は必ず医師の確認を
妊娠中はつわりや栄養不足を補うために、サプリメントや市販薬を使用する方も少なくありません。
しかし、サプリメントの中には糖分や人工甘味料、血糖に影響する成分が含まれているものもあり注意が必要です。また、ビタミンや鉄剤も過剰摂取すると消化器症状や吸収のバランスに悪影響を与える場合があります。
国立健康・栄養研究所のデータベースでも、妊娠中のサプリメント摂取には慎重な判断が必要とされています。妊婦用として市販されている商品でも、体質や体調に合わない場合があるため、「自己判断ではなく、かかりつけ医に相談すること」が基本です。必要に応じて、妊婦健診時に成分表示や摂取状況を伝えておくと安心です。
定期的な妊婦健診が早期発見と予防につながる
最後にもうひとつ大切なことは、定期的に妊婦健診を受けることです。妊娠糖尿病は自覚症状がほとんどないため、尿検査や血液検査などを通じてはじめて発見されることが多くあります。早期に見つかれば、軽い食事調整や生活の見直しだけで血糖値を改善できるケースも多いため、健診のタイミングを逃さないことが何より重要です。
また、健診では体重の推移や血圧、むくみなどのチェックも行われ、妊娠高血圧症候群や他の合併症の兆候にも早く気づくことができます。妊婦健診は、赤ちゃんの健康だけでなく、お母さん自身の体調を守るためにも欠かせない存在です。日常生活の延長線上にある「定期確認」として、前向きに受けていくことが妊娠糖尿病の予防につながります。
妊娠糖尿病の再検査になったときの対策

糖負荷試験で再検査になった場合でも、すぐに妊娠糖尿病と診断されるわけではありません。
再検査とはあくまで、初回の検査結果が基準値に近いか、体調や条件の影響で異常値が出た可能性があるときに行われる確認のための検査です。そのため、再検査になったからといって過度に不安になる必要はありません。
まずは冷静に、次の検査までの数日間を整えた生活で過ごすことが大切です。睡眠不足や極端な食事制限、強いストレスなどは血糖値に影響する可能性があります。再検査までの間は、できるだけ栄養バランスの取れた食事を心がけ、無理のない範囲で体を動かし、睡眠を十分にとりましょう。
また、医師から指示された場合は、食事内容の記録や血糖測定を行うことで、より正確な診断に繋がります。検査当日は空腹で受けることが多いため、前日の夜は軽めの食事を早めに済ませ、当日は水分を適切にとりながらリラックスして臨みましょう。
妊娠糖尿病と診断された後の対応
妊娠糖尿病と診断されたと聞くと、「赤ちゃんは大丈夫だろうか」「自分のせいかもしれない」と強い不安を感じる妊婦さんは少なくありません。ですが、現在では妊娠糖尿病に関する医学的な理解と管理方法が進んでおり、早期に対応を始めることで健康な出産を迎えられるケースがほとんどです。大切なのは、病名に怯えるのではなく、必要なことを一つひとつ実行していくこと。ここからは、診断後にどのような対応をすればよいか、段階を追ってわかりやすくご紹介します。
食事療法が治療の基本になる
妊娠糖尿病の治療は、まず食事療法から始まるのが基本です。血糖値を急に上げるような食事を避けながら、胎児の発育に必要な栄養もしっかり摂るというバランスが求められます。そのため、自己流で食事制限をするのではなく、必ず医師や管理栄養士の指導のもとでプランを立てることが重要です。
食事の基本は1日3食を同じ時間に、規則正しく摂ること。糖質はゼロにするのではなく、量や質に注意して適度に摂取することがポイントです。白米や食パンなど血糖値を上げやすい食品は、玄米や全粒粉パン、雑穀ごはんなどに置き換えると良いでしょう。また、食物繊維が豊富な野菜や海藻、きのこ類を毎食取り入れることで、食後の血糖値上昇をゆるやかにする効果が期待できます。
たんぱく質も忘れてはいけない栄養素です。鶏肉や魚、大豆製品、卵などは血糖値にあまり影響せず、赤ちゃんの発育にも欠かせません。さらに、糖質を含む食品を摂るときは「ベジファースト」、つまり野菜から先に食べ始める工夫をするだけでも血糖コントロールの効果が高まります。
間食の取り方にもコツがある
妊娠中は空腹になると気持ち悪くなったり、ふらついたりすることがあります。そのようなときに重要なのが間食のとり方です。ただし、甘いお菓子やジュースではなく、血糖値に与える影響が少ない食品を選ぶようにしましょう。無糖ヨーグルト、ナッツ類、ゆで卵、小さなおにぎりなどは、量を調整すれば間食に適しています。
必要に応じて、1日3食に加えて1〜2回の軽い間食をとることで、血糖の変動が穏やかになり、インスリンへの負担も軽くなります。ただし、間食の内容やタイミングについても、必ず医師や栄養士に相談の上で決めていくと安心です。
食事だけでコントロールが難しいときは
妊娠糖尿病の程度によっては、食事療法だけで血糖値を十分に下げることが難しい場合があります。そのようなときには、インスリン注射による治療が検討されます。インスリンは胎児に直接的な悪影響を与えるものではなく、母体と赤ちゃんの安全を守るために有効な治療手段です。注射と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、近年は針も非常に細くなっており、自宅で簡単に扱えるようになっています。
医師の指導のもとで投与量や時間を調整しながら、必要最低限の量で管理していくことになります。インスリン療法はあくまで必要なときの選択肢であり、すべての妊婦さんに行われるわけではありません。だからこそ、早めに食生活を整え、血糖値を安定させる努力が大切なのです。
産後も続く血糖管理の必要性

妊娠糖尿病は、出産と同時に自然に改善することもありますが、すべての人がそうとは限りません。妊娠糖尿病を経験した女性は、将来的に2型糖尿病を発症するリスクが高いことが、多くの研究で報告されています。
特に、出産後の体重管理や生活習慣が不規則になると、血糖値が再び高くなりやすいため注意が必要です。出産から6週から12週後には、再度ブドウ糖負荷試験を受けることが推奨されています。この検査で血糖値が正常であっても、将来的なリスクを減らすためには、定期的な健診と生活習慣の維持が大切です。
また、母乳育児はお母さんの代謝を活性化させ、2型糖尿病の発症リスクを下げる効果があるとされています。育児中はどうしても自分のことを後回しにしがちですが、健康管理も育児の一部として考え、医師や家族と協力しながら無理のない範囲で取り組むことが重要です。妊娠糖尿病をきっかけに、家族全体の食習慣や運動習慣を見直すことで、子どもにとっても健康的な環境が整います。
よくある質問と専門医からのアドバイス
妊娠糖尿病について、よくある疑問のひとつに「本当に治療が必要なのか」という声があります。軽度の血糖値上昇であっても、放置すれば巨大児や早産などのリスクが高まり、お母さんと赤ちゃんの両方に影響が出る可能性があるため、早期の対応が重要です。また、「甘いものを食べただけで妊娠糖尿病になるのか?」という疑問も多く聞かれますが、これは誤解です。
原因は体質やホルモンの変化によるもので、甘いものだけが直接の原因ではありません。ただし、妊娠中は血糖値の変動が激しくなりやすいため、食生活を整えることはリスク低減につながります。検査にひっかかった後の対応に不安を感じる方も少なくありませんが、クリニックや専門医に相談すれば、ひとりひとりに合った食事や生活の指導を受けられます。
自己判断で食事を極端に制限したり、運動を急に始めたりすることは逆効果になることもあるため、必ず医師と相談しながら進めましょう。心配なことがある場合は、早めに質問し、不安を解消することが大切です。
母子の健康のために、今できることから始めましょう

妊娠糖尿病は、特別な人だけがなる病気ではありません。誰にでも起こりうる妊娠中の体の変化のひとつです。
そのため、必要以上に怖がる必要はありません。正しい知識を持ち、日々の生活の中で食事や運動、体重管理などを意識することで、リスクを大きく減らすことができるからです。
妊娠糖尿病の検査で「ひっかかる」ことを避けるためには、妊娠前の体調管理はもちろん、妊娠初期からのバランスの良い食生活、そして自分に合った適度な運動が大切になります。
もしも再検査や診断となっても、あわてず落ち着いて対応し、医師や管理栄養士と一緒に血糖値の管理に取り組んでいけば、母体にも赤ちゃんにも負担の少ない、健康的な妊娠・出産が可能です。
そして出産後も、妊娠中に身につけた健康的な生活習慣を続けていくことが、お母さんご自身の健康だけでなく、お子さんの未来のためにも大切なことにつながります。妊娠は大きな体と心の変化の時期ですが、正しく知り、無理せず、支えを受けながら進んでいけば、安心して命を迎える準備ができるはずです。
自由が丘で妊娠糖尿病のことで、不安なことやわからないことがあれば、お気軽に当院にご相談ください。妊娠中の糖尿病に関する専門的なサポートを、当院が丁寧にお手伝いさせていただきます。あなたと赤ちゃんの健康を、心から応援しています。
関連する記事

糖尿病の兆候?8つの初期症状と自分で出来る治療方法
記事はありません